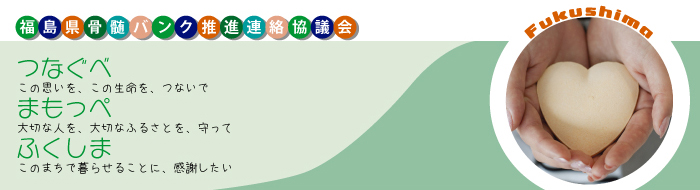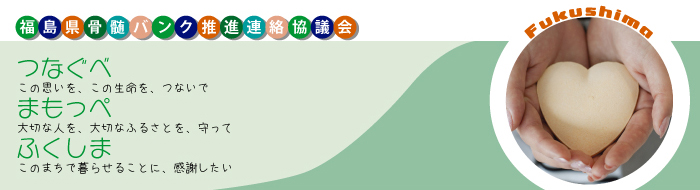●本郷 明美さん
「汽車を止めてください」。
15年ほど前のある講演会で、小説『塩狩峠』を例えに大石邦子さんが骨髄バンクへの登録を呼びかけていた。ある国鉄職員が暴走する汽車を身を挺して止め多くの客を救った――。実話をもとにした小説である。大石さんは、骨髄移植によってしか治せない病気を暴走する汽車に例え、骨髄提供によって「止めてくれ」と懇願していた。柔らかい声、おだやかな口調なのだが、それはやはり「懇願」だったと思う。臓器移植と違い、ダメージが少なく、しかも生涯何度でも提供できるという話はある意味新鮮であり、霧が晴れていくような爽快さを感じたことを覚えている。爽快さという表現は的確でないかもしれない。けれど、数万分の一の確率でこの世に存在する、同じある種の血液型をもつ人の命を私が救えるかもしれないと思うと、何か突き抜けるものがあったのだ。大石さんのそばには、白血病患者の息子さんをもつという女性がそっと立っていた。まさに適合する骨髄提供者を待っている状態なのだという。待つだけではなく、Sさんというその女性は骨髄バンクの活動に参加するようになった。多くの人がバンクに登録すれば、それだけ適合する確率は上がる。いつ病気が急変するかもしれない、もどかしい、身を焦がすようなあせりだろうと思う。しかし、その表情はおだやかで、どこまでもやさしかった。
数ヶ月後、私は骨髄バンクに登録した。
登録したことを話すと、よく「偉いね」と言われた。「偉い」という言葉に違和感があり、言わないことにしようとも思うのだが、登録者は多ければ多いほうがいい。「宣伝」しなくちゃ、という思いもあるから話す。違和感を持つのは、おそらく私の感情の流れとしてはそれが当たり前だったからだろう。だって、ひょっとしたら、あのSさんの息子さんに骨髄を提供できるのは私かもしれないのである。しかし、それはかなわなかった。私への提供依頼はいつになってもこない。
「あの、まったく依頼が来ないんですけどちゃんと登録できてますか?」
念のためバンクの事務局に電話をしたこともあった。もちろん登録はされており、「そういうこともあります」とスタッフの方になだめられる始末。
数年経って、Sさんの息子さんが亡くなったと共通の知人から聞いた。
汽車は止められなかったのだ。
登録から10年も過ぎると、次第に依頼がないのは、それはそれでよいことだと思えるようになっていた。
私と同じ骨髄の型をもつ、この世にいる誰か。数万分の一といえば、親や兄弟よりもある意味すごい縁ではないか。その縁をもつ人間が健康でいる、少なくとも血液の病気にはかかっていないという証拠なのだから。
登録していることも、バンクからのお知らせが来るときに思い出すくらいになった頃、来たのである。候補になったという通知が。近くの病院に出向き、二回ほどの検査を経て、私は最終候補となり、あとは家族の同意を残すだけになった。すでに提供者になった友人から話を聞いていたこともあり、不安はほとんどない。幸い私は自由業で、休みの融通も効く。
ところが、まったく予期していなかったことが起きた。福島に住む両親の反対である。
「今回は見送れ」という父の言葉に愕然とした。
もちろん、手術のリスクはゼロではない。身内としては反対する気持ちもわからなくはない、けれど、私がなぜ反対を予想していなかったか。それは、15年前、大石さんの講演を両親も共に聞いていたからなのだ。「汽車」の話を聞き、手術のリスクは大変低いという説明も聞き、息子さんを亡くされたSさんの話も聞いていた親が反対するとは露ほども思わなかった。私が救えるかもしれない命は、もはや漠然とした存在ではなく、日本のどこかに確かにあるのである。もう引き下がれない。なんとか親の同意なしでできないか、コーディネーターさんに尋ねたりもした。「成人なのにどうして親の同意が必要なのか?」と、少々きつく聞いてしまったこともあったかもしれない。すみません。
「どうして大石さんの話を一緒に聞いたのに反対なんてできるの?」
「ずいぶん前の話だし。お父ちゃん、お母ちゃんだって心配なんだよ」
短気な私を姉もなだめる。姉はバンクの活動をする友人もおり、提供したいという私の味方だ。
「福島のバンクの者がご両親に説明しますよ」。
姉の同意だけで進めてしまおうかと思ったとき、コーディネーターさんが言ってくださった。
私も気持ちを抑えて、父母にメールを出した。大石さんの話を聞いて登録したこと、Sさんのこと、私と同じ型を持つ誰かが、このままでは死ぬかもしれないということ、そして私には「今回」でも、その人には「今回」も「次回」もないのだということ。
「ちゃんと話聞けてよかったよ、説明してくれた人自身が提供体験がある方でね。お父ちゃんたちもだいぶ不安がなくなったみたい」
姉から連絡があった。
「説明を聞いてだいぶわかった。やってみろ」
父母の答だった。時間をかけて、周りの人の手を煩わせたが、説明していただいて本当によかったと今では思っている。手術を終えた後実感するのだが、もし両親の気持ちを無視して進めていたら、骨髄移植というせっかくの貴重な体験を家族で共有できなかっただろう。術後、次第に「提供できるのは母が私を産んで、育ててくれたから。健康だからなんだ」という当たり前のことに想いが到る。まるで自分の身体は私だけのものというように、「家族の許可なんて必要ない」と怒っていたことがとてつもなく恥ずかしくなった。
私は雑誌の記事を書く仕事をしている。4日間は仕事を休まねばならない。手術日候補の中から比較的影響のない期間にしてもらい、担当の編集者に連絡をした。
「それはりっぱなことです!仕事は大丈夫ですよ、お見舞い行きますか?」
短期間なので見舞いはご遠慮したが、温かい言葉に頭を垂れた。その間、引き受けている仕事が進まないことになるから、迷惑であるはずなのに。同業の友人にも報告する。
「何か手伝えることがあったら言ってね」と言ってくれる。
しかも友人はこう付け加えた。
「その間どうしてもしなきゃならない仕事があったら私がタダでするから!」
フリーランスは仕事を断ることが怖い。せっかくの依頼が、その会社との関係がそれで途切れてしまうかもしれないからだ。同業の友人はその怖さを実感しているので、断らず私が替りに……と言ってくれたのだ。ありがたい。涙が出た。
手術前日に入院。
おさななじみは、おにぎりやお菓子を持って通ってくれた。退屈しないようにと、本やビデオを持参してくれたこともあった。子供もいる忙しい主婦なのに、毎日欠かさず1時間ほどかけて、である。その息子さんが、電話をくれる。
「あけちゃん、病気の人がまた血を作れるようにするお手伝いをするんでしょ?すごいね。お母さんに聞いたよ。ぼくすごいと思う」
「ごめんね、骨髄移植を説明したらどうしてもしゃべりたいって言って」。おさななじみが電話を替わって謝るが、迷惑なんてとんでもない。「偉い」と言われるのには違和感があったが、素朴に「すごい」と言われると素直にうれしかった。そう、骨髄移植ってすごいことなのだ。ある人の骨髄液がある人の体に入って新しい血を作り出すのである。私が偉いんではなく、これはすごいことだ。
そして手術当日。なんと急に福島から母と姉の夫である義兄がやってきた。義兄はぽつりと、「姉が仕事で来られないから代わりに」と言った。姪っ子たちの手紙持参である。
移植の体験は私に、思わぬ副産物をくださった。いかに私が回りの人に恵まれているか、という実感。そして、そのことに対する感謝の気持ちである。
ところで、自由業の私は融通が効いたが、会社勤めの人が4日間休むのは大変だろうとコーディネーターさんに聞いてみた。
「最近は会社ぐるみで協力してくださるところも多いんですよ」
それはすごい! 4日間仕事を抜けるということは、周りの方にその分のしわ寄せがくることもあるだろう。私のように「副産物」を得ている人がたくさんいるだろうな、と思いたい。
肝心の手術である。麻酔をかけられて……目が覚めた。全身麻酔だから記憶はなく、あっけない。
針を刺した部分に痛みが残ると聞いていたのだが、驚くほど痛みもなかった。
「まだ麻酔が効いているんですか?」とお医者さんに聞くと、「いえ、もう効いてませんよ」と言う。
痛みは覚悟していたので、拍子ぬけした。
ついでに傷痕にも拍子ぬけ。髄液を取るために針で何度も刺すので、たくさんの針跡が残ると聞いていたのだが、2つ?3,4つ? そんなものである。
「右側は私が採取したので痕が一つでしょう? ほぼ同じ個所から刺すんですが、針の角度を微妙に変えることで中の骨髄に刺さる場所は違うんです。左はすいません、私じゃなかったのでけっこう、残っちゃいましたね」
術後の検診で担当の医師がちょっと自信ありげに説明してくれた。「左」担当は下手だと言わんばかりだったが、ストレートヘアを揺らして話してくれる女性医師の、その自信が気持ちよかった。「左」さんの名誉のために書き添えておくと、それでもドナー体験のある友人から聞いて予想していたより刺した穴の数はかなり少なかった。友人が提供した数年前よりも技術が進歩しているのかもしれない。
ただ、まったく覚悟していなかったのにつらかったことが一つあった。点滴である。私、実はこれが生まれて初めての入院、点滴も初めての体験だ。体に針を刺したままで長時間いるということが、あんなに苦痛だとは思わなかった。まず動きづらい、針が刺さったままだということにどうしても嫌悪感がある。
「点滴いつとれます?もう取っちゃだめですか?」
看護婦さんが来るたび尋ね、いやだいやだとぐずる私におさななじみがばっさりひとこと。
「うちの息子だって入院したときはおとなしくやってたよ。あけちゃん、恥ずかしい」
一言もない。私が入院したのは担当医師の関係で小児病棟だった。子どもたちが病気と闘うところである。ある日おさななじみが真っ赤な眼をして入って来た。何事かと尋ねると、「病気の子供たちを見てるのがつらくて。どうしてあけちゃん大人なのに小児病棟なの?
」。
私が提供した相手も十代だという。どこかの小児病棟にいるのだろうか。私はその子が、自分の子供のような気分になってきた。少し涙が出た。
手術を終え、数か月経った頃、一通の手紙が来た。提供した方のお母様からだった。まだまだ術後大変だろうに、丁寧な字で感謝の気持ちがつづられていた。そして、息子がスポーツ好きの人気者であったこと、突然の発病、骨髄移植しか治療方法がないと判断されて手術に到ったことも。そして「第二の人生なのだから力いっぱい生きなさい」と言い聞かせているという一文に涙が出た。私の、心の、「子供」である。
ひとつだけ心配がある。
「絶対その子、のんべえになるよね」
友人たちが口を合わせて言うのである。私はたしかにお酒が大好き、のんべえも認めるが、骨髄移植をして「のんべえ」が移るなんて科学的根拠はあるのか!? と反論しつつ、しかしちょっとにやりとする。心のどこかでまだ見ぬ「息子」に元気な楽しい酒好きになってほしい。時折私は祈る。日本のどこかで元気に暮らしていてと。
|